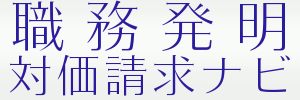相当の対価の算定基準
相当の対価はいくらになるのか?この問いについて、旧特許法35条4項は、以下の2つの事情を考慮して定めると規定するのみです。
- その発明により使用者等が受けるべき利益の額
- その発明がされるについて使用者等が貢献した程度
これらを一概に算定することは非常に困難ですから、裁判例では様々な事情を考慮して相当対価の算定がされています。
使用者が受けるべき利益とは
職務発明が特許された場合、会社は無償の通常実施権を有しますから、特許発明を自由に実施できます。したがって、この利益とは、概念的には、特許によって得られる全ての利益(≒特許の価値)から、特許発明を会社が実施することによって得られる利益(≒通常実施権の価値)を差し引いたものということになります。
前者には特許発明の実施を独占できる価値が含まれますので、例えば、他社に特許発明の実施をさせないことによってその分売上が伸びた分や、特許を複数の会社にライセンスすることによって得られるライセンス収入のような利益を全て含みます。しかし、後者は特許発明を自社で実施して得られた利益のみです。
裁判例では、使用者が受けるべき利益について、特許権の譲渡等を受けることにより、特許発明の実施を排他的に独占できる地位を取得することにより見込まれる利益としているものがあります(東京地判昭和58年12月23日昭54(ワ)11717)。
参考:東京地判昭和58年12月23日、昭54(ワ)11717抜粋
ところで、職務発明については、これが特許されたときに、使用者は、法律上当然に、無償かつ無制限の通常実施権を有する(特許法第三五条第一条)。当該発明について特許がされる前、また、特許を出願しなかつた場合には、実施権という観念は法律上存在しないが、右規定の理は、この場合にも同様に適用されるべきである。すなわち、発明について特許を出願しない場合は、理論上は万人が実施しうるわけであるが、これがノウ・ハウとして秘匿されるときは、事実上、これを知つている使用者のみが実施しうることとなるところ、この実施も、当然に無償かつ無制限のものというべきであると解される。
右の点を考慮すると、職務発明がされた場合、当該発明を無償で実施する権原を有するという点においては、使用者が従業員から特許を受ける権利を譲り受けた場合と譲り受けなかつた場合とにおいて差異はなく、職務発明について従業者から特許を受ける権利を譲り受けることにより、使用者は当該発明につき特許出願をして登録を受ければ、あるいは、これをノウ・ハウとして秘匿すれば、発明の実施を排他的に独占しうる地位を法律上又は事実上取得できる点において、右権利を譲り受けない場合との差異が生ずるというべきである。したがつて、譲渡の対価の額を定めるに当たり考慮すべき「発明により使用者が受けるべき利益」とは、使用者が発明を実施することにより受けることになると見込まれる利益を指すのではなく、右のような地位を取得することにより受けることになると見込まれる利益を指すものと解するのが相当である。
使用者等が貢献した程度とは
従業者等は会社の職務として発明を行うわけですから、そのために会社が研究資材・資金や従業者への給与を負担しており、職務発明の完成に貢献しています。よって、発明者と会社との衡平を考慮して、発明者が特許を取得した場合には、会社には通常実施権を与えられますが、発明者が会社に職務発明について特許を受ける権利を譲渡した場合には、相当の対価の算定に会社の貢献度を考慮することになります。
この会社の貢献度を算出する事情としては様々なものが考慮さられます。例えば、発明にあたって会社が負担した費用(研究費、資材、発明者の給与等)等はもちろんのこと、裁判例では、発明完成までの事情にとどまらず、権利取得過程、事業化の過程等も参酌されています。