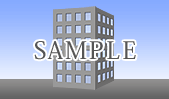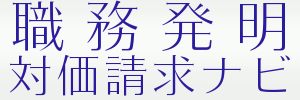実務における算定基準
裁判例においては、相当の対価の算定は以下の式で行われています。
すなわち、相当の対価は、特許によって会社が独占することができた利益に発明者が貢献した割合を乗じた額です。
独占の利益とは
独占の利益の算出方法は、会社が特許を他者にライセンスして収入を得ている(他者実施)場合と、会社が特許発明を実施している(自己実施)場合とによって異なります。
仮に、A社(自社)が1億円分、B社(競合他社)が2億円分の製品を売れるようなマーケットがあるとしましょう。特許によってこの製品の販売をA社のみが独占できることになった場合、B社が2億円の製品を売るには、A社がB社に対して特許の実施許諾(ライセンス)をする必要があります。B社がA社に支払うライセンス料は特許によって得られる利益であり、これが独占の利益にあたります。この場合、ライセンス料は、B社の売上(2億円)×実施料率といった決め方をされることが多いです。
一方で、A社のみが製品の販売を独占した場合はどうでしょうか。A社はB社のシェアを奪取できますので、単純に考えれば3億円の製品を売れるはずです。一方で、特許が無くても売り上げることができる1億円分については、たとえA社が特許を承継しない場合(職務発明をした従業員が特許を取得した場合)でも、A社には法定通常実施権がありますので、無償で製品の販売等をできることになります。したがって、特許によって増加した売上高(超過売上)の分についてのA社の利益、すなわち2億円のみが問題となってきます。この2億円の売上について、A社が特許によっていくらの利益を得たかを計算するのは難しい問題ですが、通常は、仮想実施料率を乗じて利益の額を計算します。つまり、超過売上分が他社にライセンスされていた場合と同様な利益が得られているとするわけです。
これをまとめると、特許による独占の利益は以下のようになります。
他者実施の場合
自社は特許発明を実施せず、他者にライセンスをした上で実施させている場合です。ライセンス収入が独占の利益ということになります。
自己実施の場合
特許の効果によって増えた売上分(超過売上)を、他者にライセンスしていると仮定した場合のライセンス料が、独占の利益ということになります。ここで、売上増加は一つの特許のみに起因するものではないことが多いため、ある特許の独占の利益は、その特許の寄与率を乗じて算出します。
【ご参考までに:ご存知ですか、職務発明対価算定のメカニズム(tokyo devices記事)】
超過売上とは
超過売上とは、